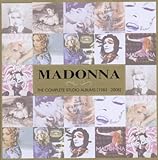もうすぐ春ですね、ちょいと気取ってみませんか、ってなもんで、今日は雨だが、生暖かかった。
ああ。そういえば、「今年は70年代ロック、聴くんだ」と年初め、思っていたんだっけ。もう、忘れちゃった。
モントローズのすべてのアルバム、聴きました。肩が凝りました。
ビー・バップ・デラックスも5枚組のアンソロジー全部、聴きました。肩が凝りました。
なんか、あれば、感想、例によって例のごとく、ここへ、ダラダラ書いただろうが、「あー音が鳴っとるなぁ」ちゅう感じで。好きな方には申し訳ない。ロックはやっぱ、肩こりますわ。えへっ。
クルマで、イエローマンの「Live At Aces Feeding In The Dancehal」(Feb. 10th, 1982 in St. Thomas, Jamaica with Aces International Hi-Fi)を聴く。肩のこりが、すーーーーーと抜けていきました。
例によって例のごとく、こっから、ダラダラ思いクソ、書くんで、興味ない人は、そのつもりで。また、かなり、データ的に間違ったこと、誤解している部分はあると思うが、オレの感じたことは、そのまま、だから、そっちの方に重きを置いていただきたい。
1982年、エイセス・インターナショナルでのRUB A DUBのライブである。
ちょっと前書いた、英国産のアスワドが81年やUB40のファーストが81年だから、ほぼ同時期にあたる。これらのUK産も、もちろん、好きなアルバムである。でも、このイエローマンのライブと比べると・・・・。
Live At Aces: Feeding In The Dancehall (with Fathead)
(今回は
アナログ時代を含め、もう、何回聴いたか、知れない。飽きるが、飽きたら、また、飽きがおさまるまで、何年か、待って、また、聴きまくる。人生のサイクルちゅうやつだ。まあ、この手のRUB A DUBのライブは他にもあり、雑音にしか聴こえない人もいるだろうが、オレはかなり聴き込んでしまう、タイプである。
(↓のような感じ フィジカル、フィジカル、の方ね)
さて、このライブ、4曲目と5曲目は「Mighty Diamonds Selection」という曲名になっているが、マイティ・ダイアモンズというコーラス・グループの「パーティ・タイム」というレコード(厳密に云うとダブ・プレートという盤なんだろうが)をかけながら、イエローマンがその曲に声をかぶせていく、平たく言えば、カラオケでオッサンが「氷雨」唸る、ような感じであろう。
4曲目は、マイティ・ダイアモンズのヴォーカルが入ったレコードをちゃんとかけて、イエローマンはゆうなれば、曲の紹介と曲が始まってからは、あの珠玉のコーラスの合間合間に「えいっ」とか「むーん」「かみせらーだ」とか合いの手を加えながら、マイティ・ダイアモンズの「パーティ・タイム」の美しいヴォーカルを思う存分、ワシらに堪能させながら、徐々に盛り上がってく。
5曲目(ちゅうても境目は無いのだが)に入ると、イエローマン全面に出てくる。今度は「パーティ・タイム」のシングルの裏面のカラオケトラック(ヴァージョン、と云う)に替わり、そっからは、天才Djイエローマンの独断場である。
イエローマンの憎いところは、この美しい「パーティ・タイム」のリズムトラックに、ゆったりと、声をリズムにのせながら、より気持ちいい(ただし、歌っている内容はなんか、めちゃくちゃワイセツなような気がしないでもない)。イエローマンが終わっても次は別のディー・ジェーが別の内容のトーストを乗せる、それが終わったらまた、別の・・・ただし、あくまでも、バックに流れているのは、マイティ・ダイアモンズの「パーティ・タイム」の演奏部分、つまり、カラオケである。
まあ、これだけの日本で言うところの「カラオケ大会」、みたいなのが、当時、いかに最先端で、ラジカルで、あったのか?
・バンドの替わりをレコードプレーヤーとレコードで行ったこと
これは当時もなにも、それよりずっと昔から日本でも、いわゆる「口パク」ちゅうやつでやっていたわけであるが、
・オリジナルの歌詞にとらわれることなく、そのリズムに沿って、誰でも、自由に歌ったり、ディー・ジェー(いわゆるラップのことなのだが、)できたこと
オリジナルが、暗い暗い黒人の奴隷時代からのあれやこれやの歌詞であったとしても、そのリズムに、極端な話、人種差別の歌詞ないしはおしゃべりをのせるヤツがいたら、その曲は、黒人排斥の歌に変わってしまうのである。逆にというか同様にというか、美しい愛の歌だって、別の歌詞をのせれば、立派な白人支配に反抗し続けるラスタ賛歌にもなるわけである。
そして、これらのことができるということは、誰でも(もちろん、それ相応の力はいる)できると同時にどんな曲でもできる、わけである。
もちろん、声がのせにくいと話にならないから、その曲は「リズムがしっかりしていないと」アカンのである。
しかし、しかし・・・嗚呼・・・。「リズムがしっかりしていない」曲を「リズムのしっかりした曲」に変えること、なんぞ、ジャマイカの音楽環境下においては「お茶の子さいさい」なのである。
それに加えて、かてて加えて、ジャマイカ独立以降、膨大な数の「リズムのしっかりした」良曲のストックがある。
(これの歴史については、固有名詞挙げていくとトンデモないことになるし、オレも混乱してしまうので、はしょる)
最強のバンドと至上の女性コーラス隊をバックにしてカリスマ的な人間が練りまくったオリジナルの歌を歌う、ボブ・マーレイ的な「レゲエ」の呪縛から解き放たれることになったのである。一つの「レコード」があれば、似たようなことができる(このへんもおおざっぱに書いてます)わけである。んっちゃちゃ、んっちゃちゃのレゲエ特有のリズムにとらわれることも、ないのである。
このしくみで、イエローマンは、70年代終わりから80年代初頭にかけて、膨大なレコードをリリースする。下ネタもやれば、コアなネタも自由自在。
かくして、ジャマイカの音楽は、その歴史の丸ごとの中から、いい音(リズムトラック)を選び出しては、カッコ良くして、そこいらの兄ちゃん姉ちゃんおっさんおばはん、爺さん婆さんから「才能」をかき集め、束になって、次から次へと気持ち良い音楽を生み出していくのである。
まあ、ほんま、ジャマイカの音楽のジャマイカの音楽、ジャマイカの音楽したところを書こうとすると、長々してしまう。
今日紹介した上のアルバムはその時の「熱気」、ボブ・マーレイという特別な「個人」じゃなく、ジャマイカが歴史ごと、束になってかかってこようとする、その瞬間の「熱気」が感じられる、ちゅうことですわ。
イエローマンはジャマイカでは差別を受けることが多いアルビノであったため、幼少期に両親に捨てられてしまう。島内の孤児院を転々とした後、多くの音楽家を輩出していることで知られるキングストン市のアルファ・ボーイズ・スクールというカトリック系私立学校で教育を受けた[2]。
U・ロイやボブ・マーリーに影響を受けたイエローマンはディージェイを志し[2]、他の多くのディージェイと同じように、ジェミナイ、ブラックスコーピオ、エイシズ、キラマンジャロ、ブラックホークなどのサウンドシステムでトースティングの技を磨いた[3]。1970年代後半にはテイスティ・タレント・コンテストというタレント・コンテストで優勝し注目を集め[4]、1980年、「Even Tide Fire」でレコードデビューした[5]。
[From イエローマン - Wikipedia]
(日本語のWikipediaで「イエローマン」があった!!!!)